「ようお前らご苦労だったな」
「何で貴様がいるんだクソババァ」
「殿下、口をお慎み下さい」
「八戒もいたのか・・・ったく」
「あぁ八戒、身体の方はもう大丈夫ですか?」
「意図的に呼吸を浅くしていたので、左程薬を吸っていませんから、ご安心を。
本当はあの童女の足音が遠ざかったところで扉なり窓なり開けようと思っていたのですが、随分早い段階で薬が充満してきたので、流石にちょっと焦りましたよ」
「災難だったな、この計画は知る人間が少ないほど都合がいいもんで、殿下とそう体格の変わらんお前さんに任せるのが一番だったワケよ」
「・・・お言葉ですが捲簾大将、僕の身長は、殿下より1寸(約3cm)ちょっと高いんですよ?」
「お前は黙ってろ(怒)」
「・・・お前達、深夜に人の部屋で、言いたい放題だな」
「失礼致しました、陛下(←棒読み)」
「殿下の不敬は皇太子傅たる私の責任。平にご容赦を(←棒読み)」
「すみませんねぇ(へら)」
「陛下、コイツどーしましょーかね?(←聞いていない)」
「・・・そこのソファにでも寝かしとけ」
「丸められてるぞ、金蝉」
周囲に影響されやすい息子の事を、しかし左程心配するでもなく面白そうに言う皇太后。
そんな彼女がこの時間、自分の宮殿ではなく皇帝の宮殿にいる理由は、
「――つまり、あんたは初めっからこうなる事を予測してたんだな?」
「皇太后様に質問する態度じゃねぇな?人に物を聞く前に、言う事はないのか。あぁ?」
「・・・・・・(自分で様付けするか!?)」
高飛車に言われてカチンとくるものの、言われた事は事実なので、真顔になって皇太后と皇帝陛下の前に片膝立ちでひざまずいた。
衣擦れの音でそれを察した計都も、倣って下座でひざまずく。
「私、玄奘三蔵は、ここにおります娘、計都を生涯の伴侶として選びました事を、皇帝・皇太后両陛下に御報告申し上げます。
つきましては、両陛下にはこの婚姻に御許可を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます」
「!!?・・・・・・っ」
驚いたのは、計都。
もう少しで顔を上げるところだったが、すんでのところで自制心が働いた。
言いたい事も聞きたい事も山ほどあるが、今の状況ではそれは許されない。
「ま、及第点といったところだな。真剣な割に敬意は足りてねぇが」
「それで三蔵、外部への公表はいつにする?」
「・・・やっぱりあんたらグルだったか」
先程の敬語の羅列は何所へやら、再び不遜な口調に戻って皇太子が顔を顰めるが、皇帝母子は知らん顔だ。
そもそも、事の発端はお妃選びの絵姿の山から出てきた、式次第の下刷りに挟まれた朧月の絵姿。
皇太后自らが持参した(運んだのは侍従だが)物にそのような物を紛れ込ませることが出来るのは、他ならぬ皇太后本人以外にない。
ということは、宴を主催した皇帝共々、朧月の正体を知っていて、皇太子に揺さぶりを掛けるためにあの絵姿を用意したと考えるのが妥当だろう。
果たして、皇太子は朧月が10年前のあの少女であると気付き、宴で名を呼ぶに至った。
結果的には丸く収まったものの、皇太后の手の上で踊らされた感の拭えない皇太子は、歯軋りせんばかりに悔しさを滲ませている。
一方で、彼等の会話しか捉えられない計都は話が飲み込めず、三つ指を突いて頭を下げたまま、混乱に陥っている。
竦み上がっている計都に、皇太后はいつになく柔らかな口調で話し掛けた。
「おい、朧月――いや、今は計都か。顔を上げな。
ンな怯える必要はねぇ。俺達はお前さんをずっと以前から知っている。最初に、お前さんがコイツと出逢った時からな」
「大方、お前達と親父が酒の肴にチクったんだろ」
皇太子が横目で天蓬・捲簾を睨み付ける。
2人の表情を見れば、答えは明らかだった。
――つまり、
10年前、皇太子――その当時は皇孫――が計都と出逢った直後、前皇帝――こちらは当時皇太子――がその様子からその心情を察し、側近であった天蓬・捲簾の2人の言葉から息子の初恋を確信したのだ。
しかもそれを、宮廷内の飲み仲間である従妹に、親馬鹿全開の顔で話したのである。
「光明の奴、そりゃあ喜んでたぜ。乳母にすら懐かなかったお前が、女童の命を助けた上、激励の言葉を掛けたんだからな。他人の事なんか完璧無関心なお前がよ」
「うっせぇな」
というか、己の気持ちを自覚すらしていなかった自分を余所に、言いたい放題の従兄妹共だ。
皇太子の暴言も何所吹く風で、皇太后は計都に再び話し掛ける。
「昨日の宴の件は、多少泳がせ過ぎた俺達にも責任がある。お前さんの働きがなければ、事態はもっと深刻になっていたんだ。改めて礼を言う」
「勿体無いお言葉にございます・・・」
「つまり、あんた達は暗殺計画の存在まで知っていた、と」
「当然だ。右大臣が流した噂だけじゃない、実際、宮廷のあちこちで不穏な動きがあった事は、天蓬達近衛府の人間の、更に一握りの者だけに内偵を命じて把握していた」
「・・・あんたが即位してからというもの、自分の意見を持たず臣下の言うなりに政を行う様を見て、俺は一度皇太后に進言したことがある。
その時は相手にされなかったが――つまりは2人して宮廷内の膿を出すための芝居を打ってたわけだな?」
「・・・俺は所詮、お前が即位するまでの、玉座を暖めるだけの存在。仮に俺が采配を揮い、良い法案を立てたとして、それが実現するまでにお前に実権が移ってしまえば、うやむやのうちに立ち消えるやも知れん。
だから俺は、短い期間に出来る事――宮廷から排除すべき人物の割り出しをしようと考えた。
今回の件で右大臣は自滅したが、右大臣が握っている情報を得られれば、左大臣も遠からず失脚するだろう。
俺が出来るのはこの程度だが・・・後は、お前なら何とか建て直すことが出来ると信じている」
「・・・御期待に添えるよう、全力を尽くします――」
「俺達がその娘について調査させたのも、人の上に立つ事が約束されているお前に必要な存在だと考えたからだ。
――計都とやら、そなたさえ良ければ、俺達はそなたを受け入れるつもりがある。
皇太子のことだ、きっとここへ来るまで何も言っていないのだろうが、ひとつこいつの事を頼まれてはもらえまいか?」
「――私・・・私など・・・・・・」
「過去を消し去ることは出来なくても、前へ進むことは出来る。
お前さんが過去に囚われずに前へ向かって歩き出す気さえあるのなら、俺達がお前さんの後ろ盾になってやるから心配は要らない。
もちろん、無理矢理というわけじゃねぇぞ。コイツが振られるのを見るのも乙だがな」
「貴様人を何だと思ってやがる?」
皇太后の立場にある人間の台詞とは思えない言葉に、計都は戸惑いを隠せない。
「相済まない計都殿。皇太后陛下は人をからかうのがお好きなのだ。
我が母はああ言うが、そなたの真の心は、宴の際に聞かせてくれた歌にあると私は思うのだが、どうだろうか?」
皇帝陛下の言葉に、計都は顔に朱を上らせた。
――この方は、心眼を有しているのかも知れない。
偽りや詭弁は、この方には通用しない、本能的にそう感じた計都は、ありのままを告げた。
「・・・陛下の、仰せの通りでございます」
伏し目がちに、恥らうように呟く計都の言葉に、皇帝も皇太后も目を細める。
「ならば、我々はお前達の婚姻を許可し、祝福しよう」
「有り難き幸せにございます」
「ちゃっかりしてやがんな、江流――いや、三蔵」
皇太后のツッコミも何所吹く風、では早速計都の部屋の準備を、と立ち上がる皇太子を余所に、計都は浮かない表情だった。
何か思い悩む様子に、皇太子は眉を顰める。
この佳人に、憂い顔は似つかわしくない。
「どうした?何か不満があるのなら・・・」
「いいえ、不満など、滅相もございません。ただ・・・」
言いよどむ計都に、皇太子は気配で促す。
「・・・今この時も、共に芸の道を歩んで来た芸妓達が尋問を受け、苦痛を受けているかも知れないというのに、私だけがここにこうしていると思うと、いつか天罰が下りそうで不安で堪らないのでございます・・・」
現在、検非違使(警察)による取り調べを受けているであろう『桃源楼』の芸妓達。
その殆どは、計都同様女将に従わざるを得ない状況で、刺客の役割を勤めていたに過ぎない。
にも拘らず、彼女達は罪人の烙印を押され、片や自分は殿上人と謁見している事実に、罪悪感を覚えずにはいられない。
そんな計都に声を掛けたのは、皇帝陛下だった。
「その心配は要らない。主犯格の女将は厳罰を免れられんが、芸妓達はその置かれた立場を考慮し、極力罪を減ずるよう計らうように言ってある。
むしろ、女将のこれまでの所業を明らかにするためには、彼女達の証言が無くてはならない。
懲罰を与えると得られる証言も得られなくなるので、検非違使も慎重に事を運ぶだろう」
計都の顔に、安堵の表情が浮かぶ。
「――・・・寛大な御処置を、有難うございます・・・!」
その様子を見ていた皇太后は、何やら思案していたが、
「確かに、同じ境遇で同じ事をやらかしているにも拘らず、片や罪人、片や皇妃ってのは、傍目にも不公平感アリアリだよなぁ。後で芸妓達の逆恨みを買う可能性だって無くはねぇ」
「!・・・・・・」
「・・・おい・・・」
「そう睨むんじゃねぇよ。本当の事だろうが。
そこで提案だが計都、お前さん、皇太子の毒見役として暫く仕えるってのはどうだ?」
「あ゛ぁ?」
「――と、仰いますと・・・」
皇太后の提案に、皇太子は眉を顰め、計都は困惑したように尋ねる。
「皇帝の場合、悟空がそれに当たる。元々は奴隷などの低い身分の人間が宛がわれた役目だ、誰がなってもおかしくはない。一方で、毒見役が皇太子に見初められたとしても不自然ではない。遥か西方の国では、毒見役から出世して一国の主まで成り上がった例もあるくらいだしな。
お前達が一緒になるのに際して、限りなく障害を無くすことの出来る方法と思うが、どうだ?」
確かに、皇太后の言う事は一理ある。
もちろん、他人から向けられる負の感情など、皇太子には痛くも痒くもないが、計都自身はそうは思わないだろう。
想う女性との婚姻が先延ばしにされるのは遺憾だが、当人を縛り付ける諸々のしがらみがそれで少なくなるなら、ここは皇太后の提案を呑む方が良いのか。
「皇太后におもねる必要はない。計都、お前の望む方を選べ。まず毒見役として宮廷に上がってのち俺のものになるか、今すぐに俺のものになるか」
「をいをい殿下、どんだけ俺様なんだっつーの」
「両思いと分かってるもんだから、相当強気ですよねー」
「もうちょっと、女性の心をくすぐる機微を学ぶべきなのではありませんか?」
「手前らまだいたのか(怒)」
「婚約を成立させるためには、両陛下の同意だけでなく立会人の存在も必要ですから」
しれっと答える皇太子傅を嫌そうに一瞥するが、今重要なのは立会人云々ではない。
皇太子は計都に向き直り、口調を和らげて尋ねた。
「――お前は、どちらを望む?」
計都の心は決まっていた。
「――・・・謹んで、御毒見の役目を拝命致しとうございます・・・」
――こうして、計都は東宮付きの毒見役として宮廷に上がった。
皇太子が朝、起き抜けに飲む井戸水から、夜、寝る前に飲む酪酒(牛乳酒)まで、皇太子の目の前で毒見するのがその務めの内容である。
皇太后の言葉が効いているので、計都はその役目が下賤な出自である己に相応であると考えて疑わなかった。
――が、
「皇太后陛下もお人が悪い」
「さーて、何の事やら」
「またまた、とぼけなさって。
『皇帝の場合、悟空がそれに当たる』っつったって、厨房で盛り付けの前に行う毒見と貴人の目の前で行う毒見じゃ、天と地ほどの差がありますぜ?」
「俺は嘘を言ったつもりはないがな」
「その代わり、詳細を誤魔化してはいますけどね」
「ありゃ、殿下も解っててやらせてるよな」
「そりゃそーだろ。アイツ、堅物に見えて結構ムッツリだからな」
「さて、いつまで目の前にぶら下げられた御馳走に我慢出来ますかね?」
「賭けるなら年を越す前で、だな」
「僕も年越し前ですねぇ」
「バーカ、そんじゃ賭けにならねぇじゃねぇか」
「あはははは」
皇太后の宮殿の一室で、葡萄酒を満たした玻璃の杯を片手に、皇太后と天蓬・捲簾がこのような会話を繰り広げていた事を、当人達は知る由もない。
そして同じ頃、町の食事処では、
「『桃源楼』は新たな経営者の下、本来の姿である高級料亭として再生することが許されるそうです。
元々料亭としての質は高いですし、刺客稼業を行っていたことは公表されていませんから、客足が戻るのもそう時間はかからないでしょう。
芸妓達は、町から外へ出る事を一切禁じられる代わりに、罪人の刺青を入れられずに釈放されるようですよ」
「入れたら入れたで、また色っぽい・・・」
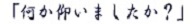
「イイエ、ナニモ。
――んで、俺にそんな事情を話すってことは、この沙悟浄様の協力が必要ってことか?」
「察しが早くて助かります。
ま、要はあの店の評判を良くするために、一、二度足を運んでいただければ、というわけで。
・・・出来れば、ご実家のお兄様などもご一緒に」
「あー・・・俺よりむしろそっちか。確かに、貿易商の若旦那のツテなら客層も良くならぁな」
「すみません、家を出た貴方に、ご実家を頼るような事をさせて・・・」
「んにゃ、家を出た理由は義理のお袋であって、兄貴とはたまに飲んだりするから気にすんなって。
でも何だって、あの店にそんなにこだわるわけ、お偉いサン達は?」
「そこは殿上人の内情というやつですよ」
「訳解んねぇ・・・」
近々皇妃となる女性の憂慮の種を摘み取りたいという、未来の皇帝の我が侭要望だとは言えず、言葉を濁して幼馴染みを煙に巻く八戒であった。
自分の周囲で交わされている会話も知らず、今日も計都はその務めを果たす。
後10日で、皇太子の我慢の限界(笑)が来るのも知らないまま。
|
―了―
|
あとがき
全ては皇太后と亡き前皇帝の思う壺だったという笑える真実。
年越し行事が面倒という理由で即位は年明けまで延期されますが、計都との婚約とゆーか実力行使(爆)は捲簾達の予想通り年内に。
ちなみに、文中の『料亭』は料理屋と芸妓を揚げる宴会場を兼ねたものを指します(祇園とかにあるアレです)。 |

読んだらぽちっと↑
貴女のクリックが創作の励みになります。 |